こんにちは、リコです。
仕事のやり取りをメールでしていると、毎回毎回

ってなるような長いメール書いてくる人いません?
この記事では、そんなメールが長い人について書いてみようと思います。
目次
カウンセラーの第一歩
心理コミュニケーション学
いきなり話が脱線しますが、私が卒業した溝口メンタルセラピストスクールでは、最初から分析学を学ぶのではなく、まず初めに心理コミュニケーション学というカウンセリング技術を学びます。
それはなぜかというと、

お前に言われたくねーよ!
って言われないため。
誰だって、自分より全然中身の薄っぺらそうな人間に、上から目線で

これまでは努力の方向性が間違ってましたね。あなたはもっと人前に出ないといけないんですよ。
とか言われたら嫌ですよね💧
分析学に基づいて有益な情報を提供できるとしても、伝える側に人間力が備わっていないと、せっかくの有益な情報が相手の心にまで伝わらなくなってしまうので、まずはきちんと人間力を鍛えましょうね、ということで、心理コミュニケーション学というものを学ぶのです。
感覚チェック
心理コミュニケーション学の講師の平間先生によると、人はそれぞれ、5感のうちのどの感覚を優先的に使っているかが異なり、どの感覚が優位かがわかると、ある程度その人の特徴が掴めるのだとか。
おおまかな特徴は、こんな感じ。
上を見る、話が飛ぶ、思いつきでしゃべる、夢を語る、旅行が好き、映画のスクリーンのように情景をありありとイメージできるetc.
話が長い、文章が長い、理屈っぽい、データ重視、冷静沈着、誰かが言ったことをいつまでも覚えているetc.
反応が遅い、下を向く、何かを触る・叩く、表現が曖昧、感覚的・直感的、理屈や質問攻めに弱いetc.
どの感覚が強い?
もちろん、人はどの感覚も使っているので、どれが強いかというのは相対的なものですし、人によっては、同じくらいの強さで差がない人もいるかもしれません。
ですが、このなんとなくの特徴を踏まえて周りの人を見てみると、

多分、あの人は体感覚が強いんじゃないかな。
あの人は視覚かな。
みたいに思い当たることが結構あります。
これが分かると、視覚が強い人にはビジュアルを示して説明した方が伝わりやすいとか、聴覚が強い人にはデータを示して説明した方がいいとか、体感覚が強い人には短い言葉で端的に伝えた方がいいとか、相手によって適切な接し方ができるようになるのです。
メールの長い人
そんなわけで、本題に戻ります。
そうなのです、メールの長い人というのは、聴覚が強いんです。
そう思ってメールの長い依頼者さんを見てみると、やはり他の特徴も当てはまっていることが多いんですよね。
男性でも女性でも、モラハラタイプが多い印象です。
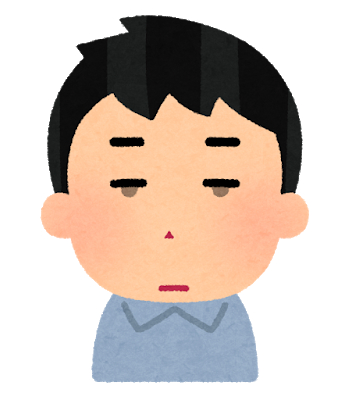
君はあの時◯◯と言っていたけれど、今の発言はそれと矛盾しているし、客観的事実に照らしても君の言っていることは間違っている。だいたい君は昔から◯◯と言ったり◯◯と言ったりしていたけれど、◯◯は△△だったし、◯◯は◇◇だったし、いつも言うこととやることが合致していないじゃないか。君がそんなだから、子どもも◯◯になってしまって、この先どうするんだ。そもそも君は・・・(以下延々と続く)
みたいに正論理詰めで相手を追い詰めるので、相手がその静かな圧に耐え切れなくなって家を出て行き、離婚を求めるというのが典型的な流れです。
だけど、理屈的に正しいことを言っているので、本人的には、なぜ離婚を請求されるのかあまりピンときていない様子。
いつまでも過去の発言を覚えているのも嫌がられるポイントですよね。
関係ないですが、私もお酒が飲めないのに飲み会でオールすると、ひとりだけ素面で酔っ払いの言動を全部覚えているので、よくみんなから嫌がられたものです(苦笑)
もったいない!!
冷静沈着で、理論的でデータ分析とか得意で、っていう聴覚が強い人の特徴って、すごい長所だと思うんですよね。
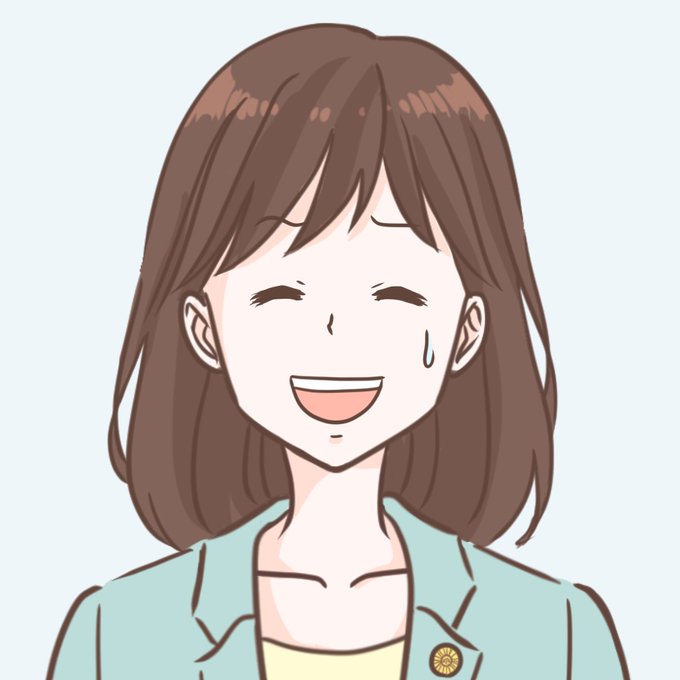
ちなみに私は多分体感覚派・・・
だけど、やたら話が長くてうんざりされるとか、理詰めで相手を追い詰めるとか、過去の発言で揚げ足取りをするとか、よくない面ばかりがクローズアップされてしまって、望まない離婚に至っている人が多い気がするのです。
自分のことを客観的に見るのって、なかなか難しいと思うのですが、メールが長いかどうかというのは、結構判断しやすいのではないでしょうか。
人から「メールが長い」と言われたことがある人、自分でも長い自覚がある人、いませんか?
特に人間関係に不満がなければいいのですが、パートナーとの仲がなんとなくうまくいかないとか、妻・夫に避けられている気がするとか、そんな方は、もしかしたら聴覚が強い人の特徴がよくない方向に働いているかもしれません。
知らずに理詰めで相手を追い詰めていないか、過去の発言をいちいち指摘したりしていないか、一度見直してみませんか?
相手との仲が改善して、気づかないうちに離婚に突き進んでいた道を軌道修正できるかもしれません。



